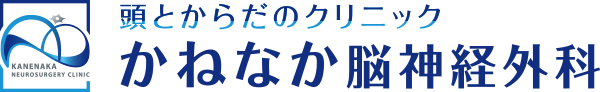-
CTの簡単な歴史?
2025.03.29画像診断部のKです。今回はCTのお話です。読み物として気楽に読んでください。
CTは「Computed Tomography」の略で、日本全国で普及しています。
このTomographyとは断層撮影という意味で、任意な断面が得られます。Computed Tomographyとはいわば「得られた信号をコンピュータで処理した断層撮影」という感じでしょうか。
この断層撮影ですが、一昔前(以上?)に行われていた検査です。当時はアナログフィルムが主で、このフィルムとX線が出る装置(X線管球)を反対方向に移動し、任意の深さの画像を得ていました。
これに対してCTはX線管球を被写体の周囲で回転させて、検出器でX線を受けそれをコンピュータで処理し、断面の画像(よく輪切り画像と表現されます)を得ます。これを目的の範囲(例えば脳全体)まで繰り返していくわけです。
ちなみに最初の商業CTは意外ですが、レコード会社のEMIが開発費を出しています。これはあのビートルズの売り上げによるものが大きいらしいです。日本ではEMIと関係にあった東芝が1975年に輸入し、東京女子医大が導入したのが始まりです。その後、東芝メディカル(現キヤノンメディカル)で国内生産が開始されました。
最初期のCTは画像を一枚出すのに約7分はかかっていました。そのためまずは脳からの運用が主でしたが、これまでは分からなかった脳の画像が得られることは非常に有用だったと思います。これが技術の進歩で撮影時間も速くなっていったのですが、1986年に画期的な技術で、現在でも主流であるヘリカルCT(らせんCT・スパイラルCT)が開発されました。
今までは寝台を移動→X線管球が一回転(撮影)→寝台を移動→…、以下撮影範囲終了までを繰り返していました。これは撮影時間も長く、肺や腹部などで息を止める場合も複数回繰り返していました。
それがヘリカルCTではX線管球が連続して回転→その中を寝台が撮影範囲まで移動(撮影)します。(被写体側から見ると、寝台も動いているためX線管球の軌跡がらせん状に見えるため、こういう名称がつきました。)
このヘリカルCTにより撮影時間ははるかに短時間化でき、肺や腹部も一回の息止めで撮影可能となりました。また今までより薄いスライスの画像も可能となり、一回撮影をして後からシャープな任意の断面の画像を作成できるようにもなりました。
これはCTの発明同様に画期的であり、体の血管を撮影したり、癌の評価(どちらも造影は必要ですが)等の撮影技術も構築されていきました。
一列から始まったヘリカルCTですが、現在ではさらに進化させたMDCT(Multi Detector CT:多列検出器CT)もしくはMSCT(マルチスライスCT)となり、さらなる高速化と薄いスライスが可能となっています。
当院でも16列のMDCTを導入しており、脳はもちろんのこと肺や腹部、四肢といった心臓以外の全身の撮影を行なっております。検査をご希望される方は、問診時にお申し付けくださいますようお願いいたします。
最後に、最初に述べたCTではない通常の断層撮影ですが、現在は乳腺(マンモグラフィ)撮影にデジタル化と共に、トモシンセシスという名称で応用されているのを紹介して今回は終わりにいたします。
最新の記事
- 2025年03月29日
4月から新たに脳神経外科医師が加わります - 2025年03月29日
CTの簡単な歴史? - 2025年03月24日
転倒を予防して、いつまでも元気に - 2025年03月09日
季節の変わり目には頭痛が付きもの - 2025年03月07日
脳ドックについて